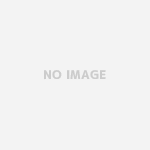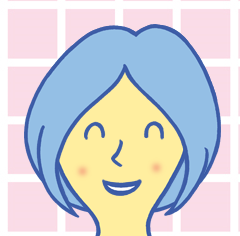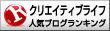※ページに広告が含まれる場合があります。

今日は第一段階・技能教習4限目、左カーブと障害物への対応について書きます。
目次
左カーブの曲がり方
前回の教習では、さまざまな角度の右カーブを通行する方法を学びました。
国産車のほどんどは右側にハンドルがついていて、その位置から見た視界が、運転者にとってのスタンダートになります。
その場合、右にカーブする時と左にカーブする時で、フロントガラスから見える範囲が変わります。
この感覚に慣れて、スムーズにカーブを曲がれるようにします。
走行位置と進路の取り方
左にカーブする際には、右カーブよりも早くに曲がり角の入口が見えなくなることを踏まえ、カーブを捉えておく必要があります。
曲がり角の入口にさしかかったら、見えている部分から死角をイメージしてハンドルを回します。
そして曲がり角の出口では、進行方向を見て、ハンドルを戻すタイミングをはかります。
障害物への対応
前方の路上に障害物がある時は、その状況を早めに読み取り、安全な進路と速度を選べるようにします。
障害物とその付近の情報の取り方
障害物がある時は、以下の点を読み取ります。
・道幅…障害物の大きさ、自分の車と対向車の大きさ
・対向車…距離、速さ
進路変更の判断の仕方
①対向車が遠い時、または遅い時
余裕を持って通過
②対向車が小さい時
左右の間隔、速度に注意しながら進路変更する
③対向車が近い時、速い時
一時停止。その際、障害物に近すぎない距離を保ち、中央線に対してまっすぐに止まる。
安全な通行の仕方
①障害物とのあいだに十分な余裕がある時は、あまり速度を落とす必要はない
②障害物や対向車とのあいだに十分な余裕がない時は、速度を落として慎重に
進路変更をする時には、前方だけでなく、側面の窓から後方も確認して、方向指示器で合図を出して通行します。
まとめ
技能教習も4時限目です。最初に学んだ運転席の調整やエンジンのかけ方などは、流れでこなす感じになります。
私はハンドブレーキの扱いで、ちょこっとてこずりました。
ハンドブレーキは以下の方法で操作します。
かける時:ボタンを押さずに引く
戻す時:ボタンを押して一度軽く引き、完全に下に戻す
慣れれば感覚的にできるようになると思います。
(2018/4/19 上記に訂正を加えました)
前回はバスが到着して、その後に技能教習を続けて2コマ受けたため、余裕もなく、あいだにおさらいをする間もありませんでした。
けれども今回は、学科教習→技能教習の順に行ったので、気持ちをクールダウンさせて、ゆとりのある状態で技能教習に臨むことができました。
落ち着いて運転することができて、大切なポイントもしっかり頭に入りました。
予約が取れると、できるうちに先に進みたいと思いがちですが、自分に合ったペースで教習を進めることが大切なんですね。
免許取得に取り組んでいるみなさん、これから教習所に通おうと考えているみなさん、一緒にコツコツ進めていきましょうね。
【スポンサーリンク】
![]()