※ページに広告が含まれる場合があります。

今日は予定通り、教習所の入校式に行ってきました。
実は前日の夜、何だか寝つけなくて睡眠不足だったため、初日の学科教習もあることですし、参加するか別の日に延期するかを迷っていました。
けれども、今回は技能教習(運転に必要な操作を学ぶ教習のこと)はありませんし、次にスケジュールが合うのは1週間も先になってしまうので、予定通り参加することに決めました。
おさらいも兼ねて、どんなことを行ったかを書きます。
目次
入校式の内容
前回の「『入校式』の流れを予習」という記事にも書きましたが、入校式では大きく分けて、この3つを行いました。
・入校式
・適性診断
・学科教習
入校式
この「入校式」の時間は、教習についての全体的な説明です。
その内容をざっと挙げると、このようになります。
・今日一日どのような流れで進めて行くのか
・「入校手続き」で配布されたテキストのおおまかな内容や、いつ何のために使うのか
・学科教習や技能教習を行う場所について
・教習所での基本的なルール(何分前に教室に入る、など)
・教習するにあたって覚えるべき期限
・教習の流れ
・教習の予約方法
これらの基本的な内容に加えて、その時の先生による独自のトークなども交えて、入校式は終わりました。
ちなみに、私の通っている自動車学校の教室は、高校や大学などの普通教室より、収容人数が少ないような、小さめの部屋という印象を受けました。
適性診断
初めの入校式のあと、休憩時間をはさんで、次は適性診断というものを行いました。
義務教育の学校で行った知能検査、会社によって入社試験や面接などで行う適性検査に似た内容です。
先生の指示に従い、時間などのルールを守って行います。
1コマ(50分)ものあいだ、ずっと検査を続けるなんて疲労しそうに思っていましたが、説明を交えて進んで行き、あっという間に1コマが終わりました。
個人的に、先生がユーモアを交えて説明するのが楽しくて、テンポ良く進んだように思います。
学科教習1
教習は、技能教習と学科教習に分かれています。
そして各教習は、第1段階と第2段階からなる、2つの段階に分かれています。
さらに各段階はいくつかのステップで構成されています。
本日最後の1コマは、さっそく第1段階の「学科教習1」が始まります。
テキストに添って、途中でDVDを観たり、先生の話を聞きながら進んでいきます。
ここでは、車とは何かという分類にはじまり、運転をするにあたってのモラルや、禁止事項、交通法令の目的や心得などを学びます。
はじめの学科教習であり、基本的な内容ついて学びます。
それでもテキストだけ見ると、実に多くの内容に触れていて、私のように本当に運転に関して知識がない人にとっては、すべて覚えるのは大変だと感じるかもしれません。
テキストに書かれていることは、もちろんどれも運転するにあたって必要なことなのですが、すべてを暗記するというよりは、ポイントを押さえて頭に入れていくのがいいと思います。
これは先生も言われたことなのですが、先生がアンダーラインを引くように指示したところ、そして〇(丸)で囲ったところなどは、覚えるべき大切な部分です。
試験に出るからというだけではなく、実際に運転をするようになった際に、とっさの判断を求められるような事柄も含まれるので、きちんと覚えるようにします。
まとめ
今日は「入校式」の内容について、まとめてみました。
さっそくテキストを使って学習したので、このあときちんと復習をしておきます。
そうそう、今日は同じ教室で学科教習を受けた方、何人かとお友達になりました。
帰り際に、「お互いマイペースでがんばりましょう!」と言って別れました。
同じ目的に向かって励まし合う人がいるって、嬉しいものです。
それぞれがニコニコの笑顔で、免許を手にすることができることをイメージして、これから教習を進めていきたいと思います。


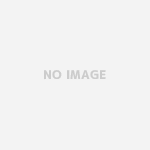


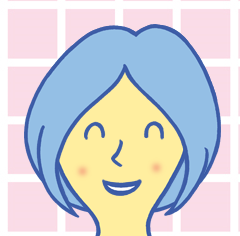
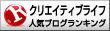

[…] 『入校式』に行ってきました […]